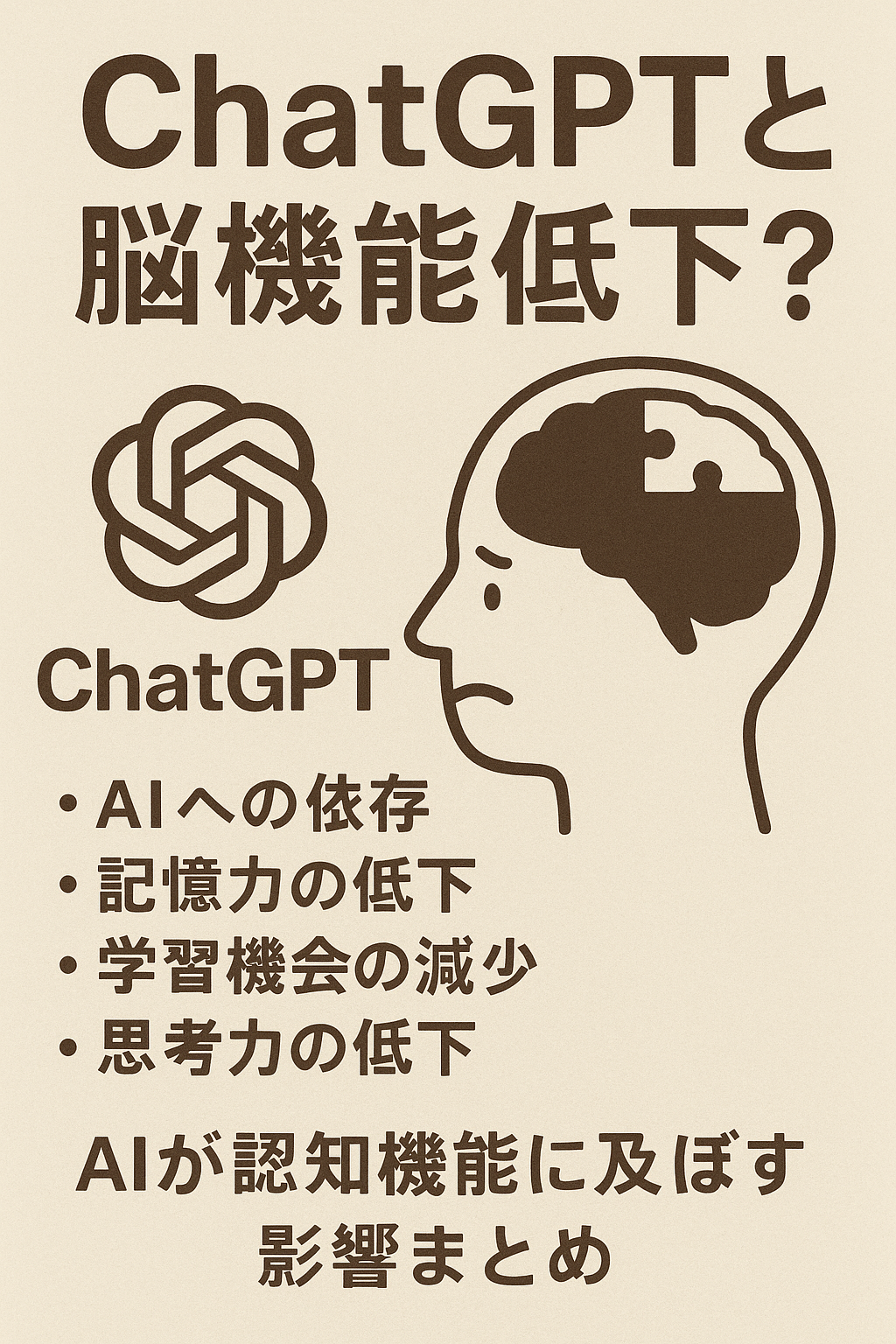
ChatGPTと脳機能低下?AIが認知機能に及ぼす影響まとめ
概要
MITの最新研究によると、ChatGPTなどのAIを使った文章作成は、脳活動の低下や記憶力の低下、自発的思考力の減退を招く可能性があると示唆されました。AIの利便性が高まる一方で、脳への影響や学習・創造性へのリスクが改めて問われています。
1. MIT実験の内容と主な結果
- 実験概要
- 18~39歳の54名を対象に、3グループ(ChatGPT使用、Google使用、自力執筆)でライティング課題を実施。
- 主な発見
- ChatGPT利用グループは記憶力が最も低く、脳活動も最も低下。
- 脳波(EEG)計測で、記憶や情報処理に関与するα波・θ波の活動が大きく減少。
- 時間の経過とともにAI依存が強まり、独自執筆が減少。最終的には「AI生成文のコピペ」に近い状態に。
- 英語教師2名は「魂が抜けたような内容」と評価。
2. AI依存が与える学習・記憶への影響
- 再現課題の結果
- 最初から自力で書いた人は、内容をよく覚えており、集中力・脳活動も高かった。
- AI依存グループは「自分の書いた内容を一文も再現できない」ケースも多発。
- 逆に「最初は自力→後からAI活用」グループは、最も創造的かつ記憶定着も良好だった。
3. 子ども・学習者へのリスク
- 研究者の警告
- 「ChatGPTを小学校などで無批判に導入するのは危険」と指摘。
- 子どもや若年層の脳発達に悪影響を及ぼす懸念。
- 他研究の知見
- 2025年5月のハーバード大学レポートでも「AI利用者は作業が速いが、動機づけが低下」と報告。
- AIは感情や意思決定能力にも影響を及ぼす可能性がある。
4. AIは「脳の代替」ではなく「増幅器」として活用を
- 結論
- ChatGPT自体が悪いわけではなく、「思考の代用」にしてしまうと認知機能が低下する。
- AIはあくまで「補助ツール」として活用し、人間の思考・創造力を主体に据えることが重要。
- 適切に使えば、AIは能力を高める「増幅器」になり得る。
5. 実践のヒント
- AI活用時のポイント
- まずは自分で考え、下書きやアイデア出しにAIを活用する
- AIの提案を鵜呑みにせず、自分の判断や編集を必ず加える
- 子どもや学習者には「自分で考える」機会を十分確保する
まとめ
AIは便利な道具ですが、使い方を誤ると「脳の筋トレ不足」を招きかねません。自分の思考力・創造力を鍛えつつ、AIは“増幅器”として賢く使うことが、これからの時代の学び方・働き方の鍵となります。