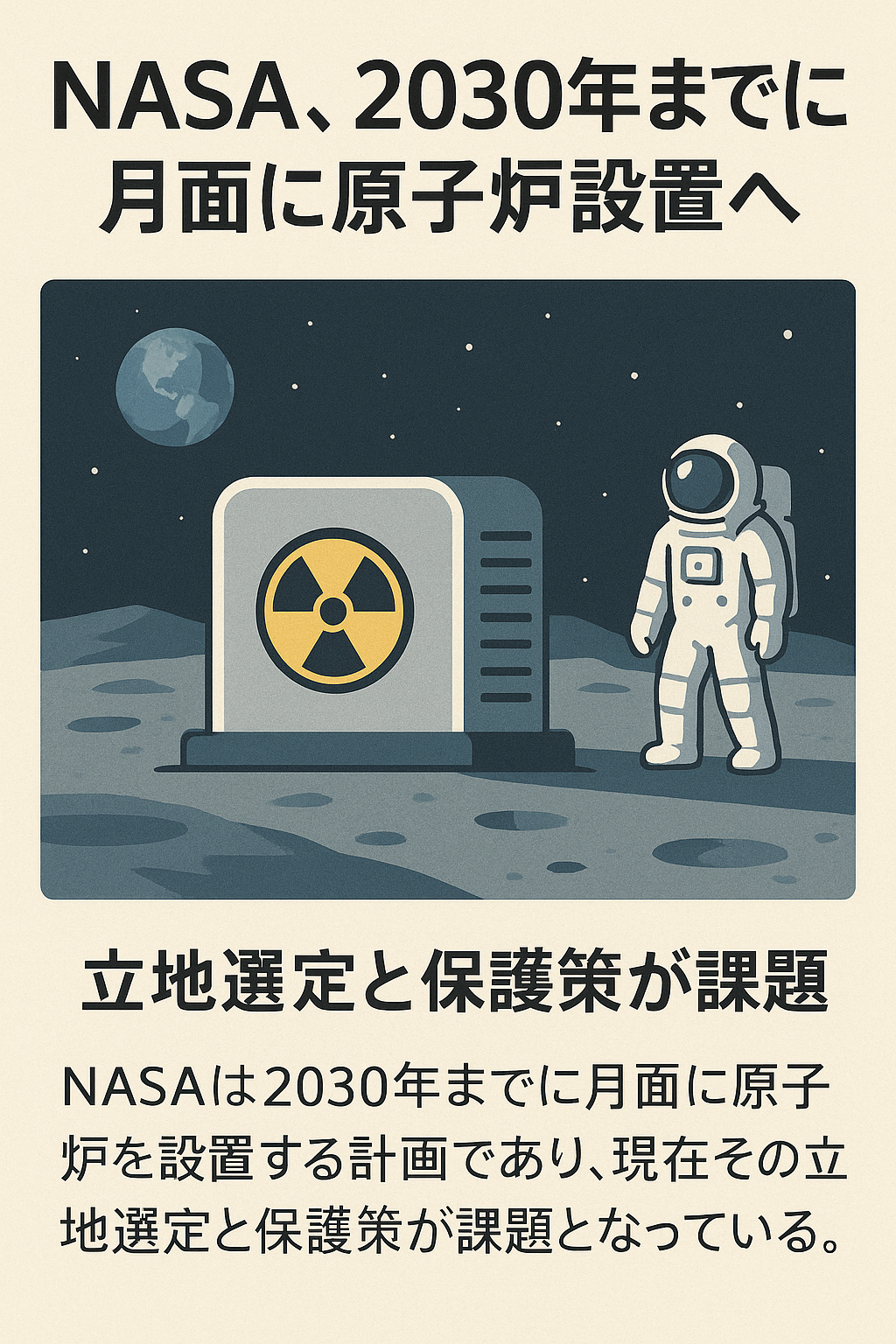
まとめ記事:NASA、2030年までに月面に原子炉設置へ ― 立地選定と保護策が課題
米国は2030年までに月面に**核分裂炉(原子炉)**を設置し、持続的な有人探査と将来的な火星探査のためのエネルギー基盤を整える計画を進めています。2025年8月、NASAのショーン・ダフィー長官代行が正式に発表しました。この動きは、中国が同年に初の有人月面着陸を目指す中、地政学的にも大きな意味を持ちます。
原子炉設置の目的と意義
- 月面の冷たい長い夜にも安定して電力を供給できるため、月面基地の維持・建設に不可欠。
- 将来の火星探査では、太陽光が弱いため核エネルギーが必須となる。
- 水や酸素の抽出、燃料(酸素+水素)の製造など、月資源の利用を可能にすることで、輸送コストを削減。
立地選定の最大の鍵:水氷の存在
- 1990年代の観測で、月の極域(北極・南極)の「永久影クレーター」に水氷が存在する可能性が示唆されている。
- NASAのアルテミス計画は南極を重点的に調査・着陸地とする方針。
- 水氷は生命維持・燃料供給の資源として不可欠であり、原子炉はこれに近接して設置する必要がある。
現在、月周回衛星による観測データが蓄積されており、候補地の「水氷ホットスポット」が特定されつつある。ただし、確定には地上調査が必須。NASAの探査機「VIPER(極域資源探査ローバー)」がその役割を担い、早ければ数年以内に詳細データが得られる見込みです。
防護の課題:着陸時のレゴリス噴射
- 月着陸船は着陸時に大量の砂塵(レゴリス)を巻き上げるため、周囲の設備に深刻なダメージを与える危険性がある。
- 1969年のアポロ12号では、163m離れた探査機「サーベイヤー3」に腐食痕が確認された。
- 今後のアルテミス大型着陸船では、さらに大規模な噴射被害が想定される。
対策案:
- 自然の地形(大岩の陰や地平線の向こう)に設置。
- 一時的に大きな岩で遮蔽。
- 最終的には専用の発着パッドを建設して被害を防ぐ必要がある。
原子炉の電力自体が、この発着場の建設にも活用できると期待されています。
今後の展望
- 原子炉設置は月面基地建設の出発点となり、長期的には火星探査にも応用可能。
- 水氷活用・インフラ整備・防護策など、課題は多いが、一歩ずつ解決することで人類の太陽系進出の足掛かりとなる。
- 「月でできれば、火星でもできる」――NASAはそうした技術の蓄積を目指しています。