2025年8月5日、私たちが普段意識しない「一日」の長さが、ほんのわずかではあるものの記録的に短くなりました。この日、地球の自転により1日の長さが通常よりも1.25ミリ秒短くなったのです。人間には感知できない微細な違いですが、これは科学者たちを驚かせている現象の一部です。
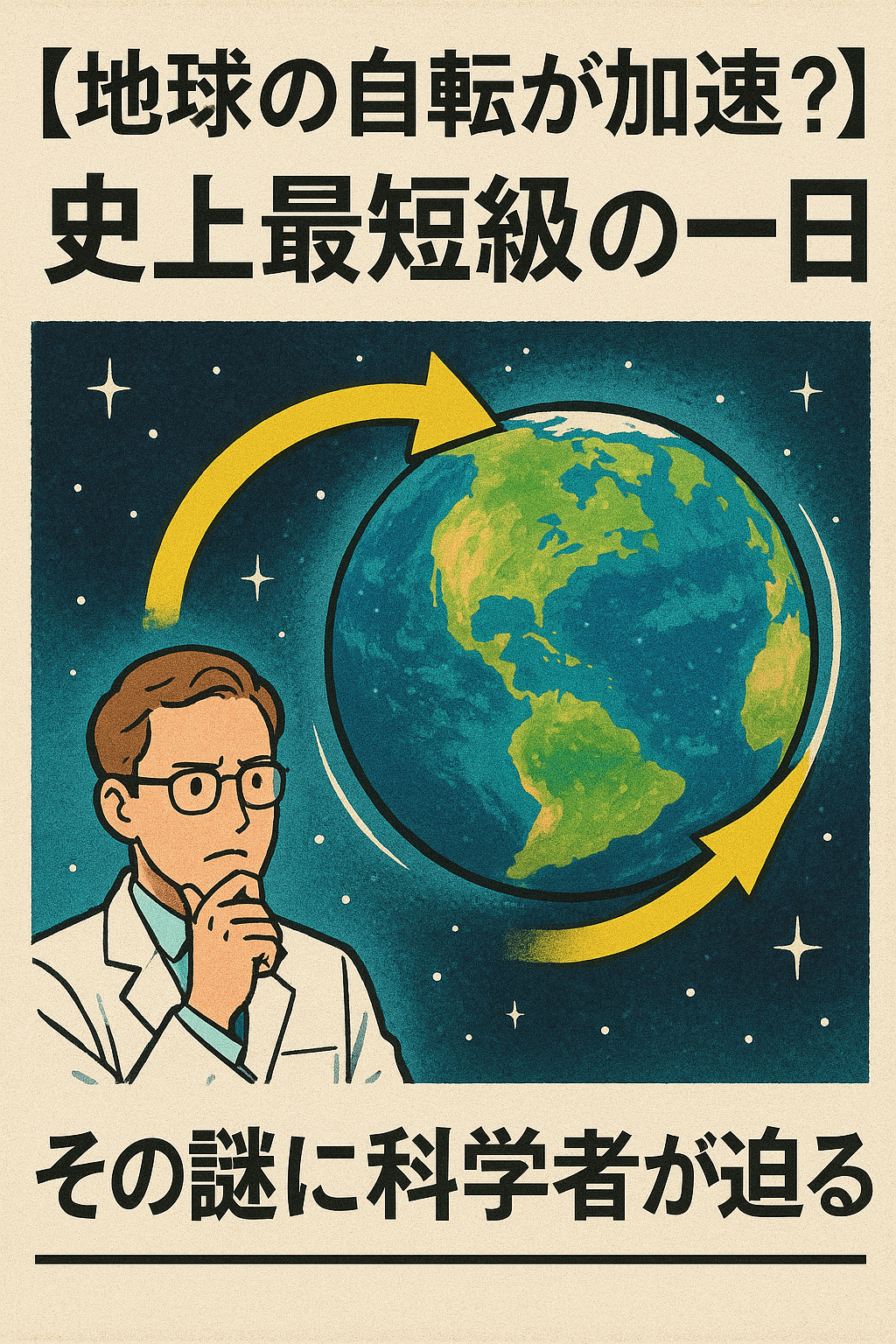
【地球の自転が加速?】史上最短級の一日──その謎に科学者が迫る
◆ 地球はなぜ加速しているのか?
長年にわたり、地球の自転は月の引力による潮汐摩擦の影響で徐々に遅くなっているとされてきました。実際、1973年以降の記録でもその傾向が見られます。
しかし、近年この動きが逆転。地球の自転速度が加速しているという観測結果が報告されています。2024年7月5日には、記録史上最も短い「1日」(86,400秒から1.66ミリ秒短い)も観測されました。
【参考:2025年の短縮日】
- 7月9日:1.23ミリ秒短縮
- 7月22日:1.36ミリ秒短縮
- 8月5日:1.25ミリ秒短縮
これらの予測には、**月の位置(とくに赤緯)**が関係しており、月が地球の赤道に対してどのような位置にあるかで、潮汐力が変化し、自転速度にもわずかな影響を及ぼします。
◆ 原因は地球の「内部」?
この短期的な変動は月の影響で説明できますが、長期的な加速の原因は不明です。有力な説としては、
- 地球内部の液体核の回転減速
- それによって地殻の自転速度が相対的に増す
- 地球規模の質量分布の変化(氷の融解による質量移動など)
などが挙げられていますが、どれも決定的な証拠には至っていません。
◆ 今後の影響は?負のうるう秒の可能性
このまま地球の自転が加速を続ければ、「負のうるう秒(leap second)」が初めて導入される可能性があります。通常のうるう秒は1日を「延ばす」ために追加されますが、今回は逆に1秒を削除する調整が求められるかもしれません。
その導入が現実になるのは早くて2029年頃と予測されています。
▼ まとめ
- 地球の「一日」が過去最短クラスに
- 月の位置が短期的な自転変化に影響
- 根本原因は地球内部の運動にある可能性
- 将来的には「負のうるう秒」が導入されるかも
地球の自転速度の変化は、天体物理学や時間の定義に大きな影響を与えるかもしれません。目には見えない「1日のズレ」に、これからも注目が集まりそうです。