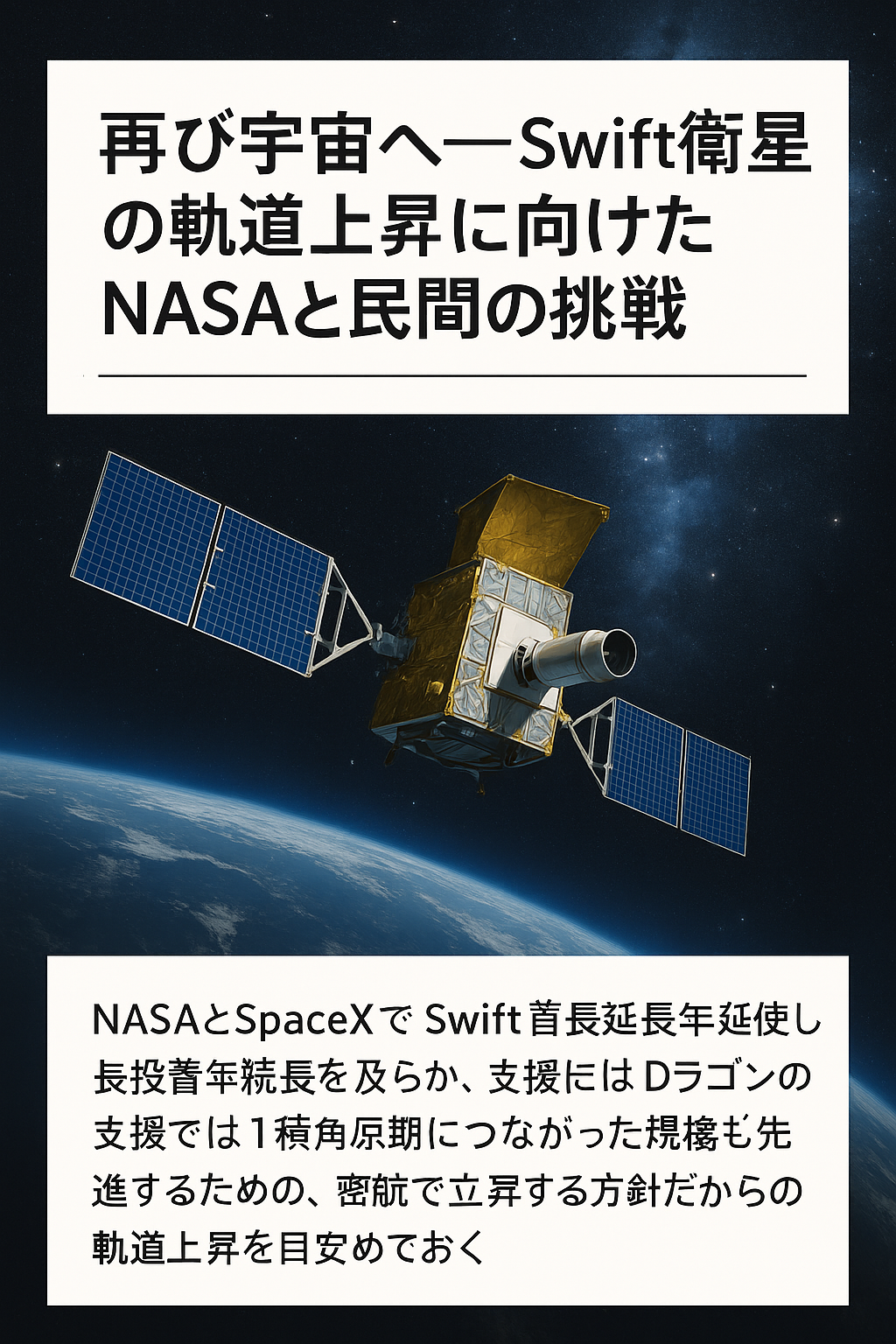
【再び宇宙へ──Swift衛星の軌道上昇に向けたNASAと民間の挑戦】
◆ 軌道降下の危機が、新たな技術実証のチャンスに
NASAの「ニール・ゲーレルス・スウィフト天文台(Swift Observatory)」は、2004年の打ち上げ以来、ガンマ線バーストなどの高エネルギー宇宙現象を監視し続けてきた観測衛星の中核的存在です。
しかし現在、太陽活動の活発化によって地球大気が膨張し、Swiftの低軌道が加速度的に減衰。このままでは、いずれ大気圏に突入し、寿命を迎えることになります。
この危機的状況をチャンスと捉え、NASAはアメリカ企業との連携による軌道上昇(オービットブースト)技術の実証を検討しています。
◆ 軌道上昇を検討する3社とその技術
NASAは以下のアメリカの小規模宇宙関連企業3社と協力し、Swiftの軌道上昇の概念設計を進行中です:
🔧 Cambrian Works(バージニア州レストン)
🔧 Katalyst Space Technologies(アリゾナ州フラッグスタッフ)
→ 両社はNASA SBIR(中小企業イノベーション研究)プログラムフェーズIIIにおいて、各社15万ドルを受給し、設計調査を開始。
🚀 Starfish Space(ワシントン州シアトル)
→ すでに開発中の小型衛星用推進&点検機能「SSPICY」をSwiftに適用できるかを解析中。
「このようなタイミングで、民間企業と連携して革新的な技術開発を試すことはNASAのSBIRの本来の目的です」
― クレイトン・ターナー(NASA 宇宙技術ミッション局)
◆ Swiftミッションの意義とこれまでの貢献
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 打ち上げ年 | 2004年 |
| 主目的 | ガンマ線バーストの即時検出とマルチ波長観測 |
| 成果 | 爆発する恒星、活動銀河、彗星、太陽系内の天体まで広範に観測 |
| ネットワーク | NASAの他の望遠鏡と連携し、宇宙の動的変化を即座に追跡可能な体制を構築 |
「SwiftはNASAの宇宙望遠鏡ネットワークの要でした。今、それを再活性化する技術的挑戦が始まっています」
― ショーン・ドマガル=ゴールドマン(NASA天体物理学部門)
◆ 技術実証の狙い:商業宇宙産業との相乗効果
- 軌道上昇ミッションが正式決定されたわけではありませんが、Swiftの現状は**「迅速な実行と民間連携の好機」**とNASAは判断。
- この実証により、将来的な宇宙機の延命・再活用・サービス化(サービシング)技術の進展が期待されます。
◆ SBIR(America’s Seed Fund)とは?
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 従業員500人未満の中小企業・スタートアップ |
| 特徴 | 株式希薄化なしで資金提供(非希薄型) |
| 目的 | 技術の早期開発支援 → NASAミッションへの適用 & 民間展開支援 |
◆ Swift運用体制と国際連携
Swiftは以下のパートナーと連携して運用されています:
- NASAゴダード宇宙飛行センター(米)
- ペンシルベニア州立大学、ロスアラモス国立研究所、ノースロップ・グラマン
- 英国宇宙庁、レスター大学、イタリア宇宙機関、ブレラ天文台など
🌌 結論:老兵にもう一度、宇宙での役割を
20年にわたり宇宙観測を支えてきたSwiftが、今再び、産業界の挑戦と科学の融合の象徴として新たな局面を迎えようとしています。
「Swiftの寿命延長だけでなく、アメリカの宇宙産業の実力を示す機会にもなる」
― NASA幹部コメント
本記事は、記事「NASA Explores Industry Possibilities to Raise Swift Mission’s Orbit」のまとめ記事です。