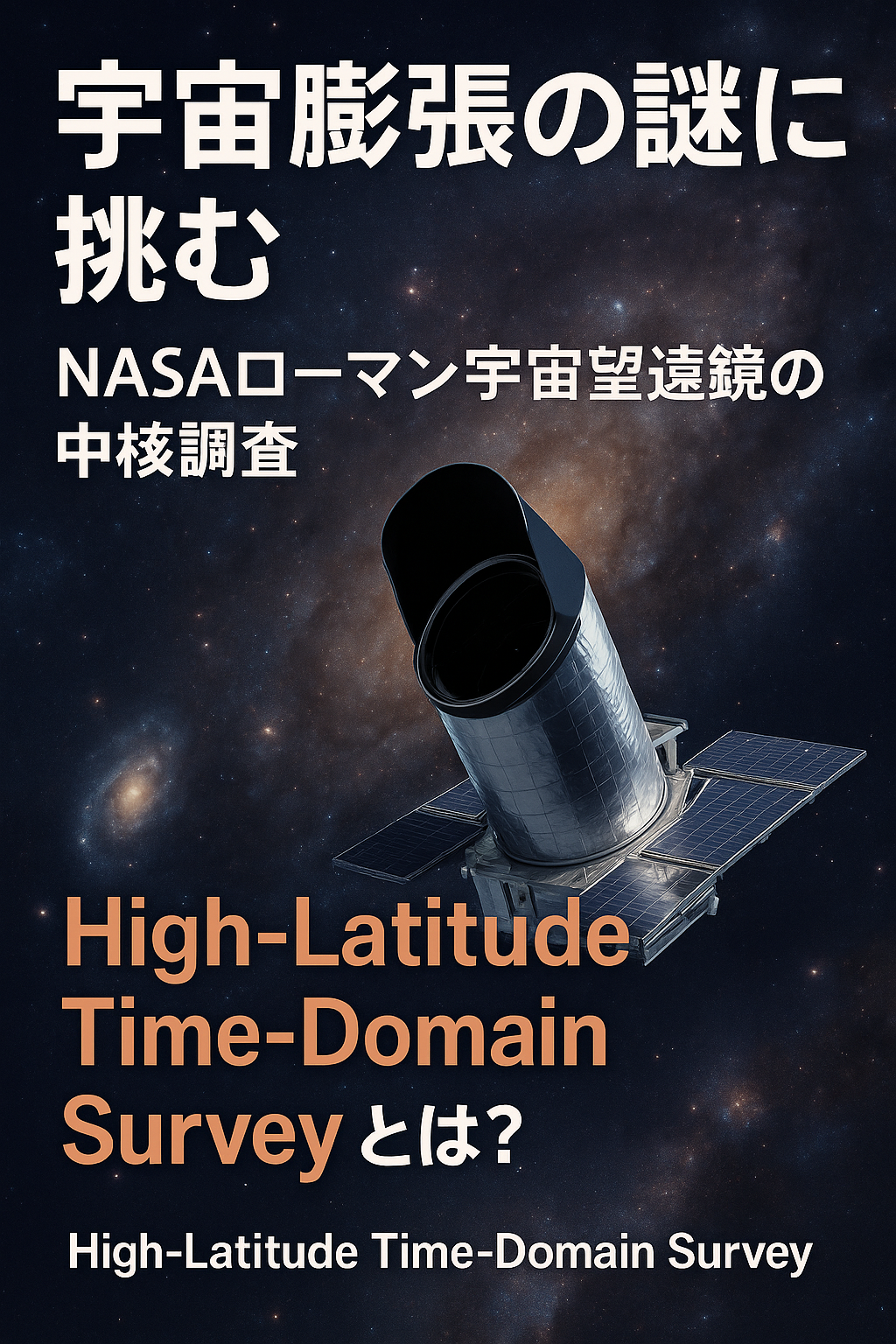
【宇宙膨張の謎に挑む】NASAローマン宇宙望遠鏡の中核調査「High-Latitude Time-Domain Survey」とは?
◆ ローマン宇宙望遠鏡、2026〜2027年に打ち上げへ
NASAが開発中のナンシー・グレース・ローマン宇宙望遠鏡(Roman Space Telescope)は、2026年秋〜2027年5月までの打ち上げを目指し、次世代の宇宙観測を担う“ディスカバリー・マシン”として注目されています。
その最大の特徴は、ハッブル望遠鏡の200倍の視野をもつ赤外線カメラ。同等の解像度と感度で、膨大な量のデータを一挙に収集可能です。
◆ 中核科学プログラムの一つ「高銀緯時変サーベイ」
ローマン望遠鏡の観測時間の**約75%**が、中核3大調査(コア・サーベイ)に充てられます。そのうちの一つが:
🔭 High-Latitude Time-Domain Survey(高銀緯時変サーベイ)
- **銀河面の外側(高銀緯)**を観測対象とし、時間とともに変化する天体(超新星、合体する中性子星など)を捉える
- 目標は、宇宙膨張の履歴を明らかにするIa型超新星を数万個規模で検出
◆ ダークエネルギーに迫る:Ia型超新星がカギ
- Ia型超新星は「宇宙の距離測定の標準ろうそく」として用いられ、その明るさの既知性から距離と膨張速度の関係を割り出せます。
- ローマンは、宇宙誕生約30億年後(約110億年前)の超新星まで観測可能で、これまでの膨張履歴の2倍以上の時間軸をカバーします。
🔍 最新研究では、ダークエネルギーが時間とともに変化している可能性も示唆されており、ローマンの観測がその検証に不可欠となります。
◆ 観測手法と構成
⏱️ 時変天体を検出する手法
- 同じ空を複数回観測し、過去の画像と**「減算処理」**を行って変化した部分(新しい現象)を抽出
- 主な観測は5年のミッション期間中、中心の2年間で5日ごとに定期観測、計180日分
- 初期には15日分の基準画像も取得
🧭 2つの観測ティア(層)で構成
| ティア | 面積 | 主な目的 |
|---|---|---|
| ワイド(広視野) | 約18平方度(満月90個分) | 約70億年前までの超新星検出 |
| ディープ(高感度) | 約6.5平方度 | 最大100億年前の暗い現象の検出 |
🌍 観測領域
- 北天と南天にそれぞれ1か所ずつ設定
- スペクトル観測は南天はローマン本体、北天は地上のスバル望遠鏡が担当
◆ 観測対象:極めて希少かつ遠方の現象も捉える
ローマンが捉える予定の変化天体は以下の通り:
- 🌟 Ia型超新星(宇宙膨張の尺度)
- ⚫ 潮汐破壊現象(超巨大ブラックホールが星を引き裂く)
- 💥 対不安定型超新星(星が完全に崩壊し、残骸を残さない)
- 💫 キロノヴァ(中性子星の合体)
🧠 音で学べる!観測対象のソニフィケーション(音声化)も公開中
- 時間軸と共に遠ざかる現象を音で表現
- 各現象に異なる音が割り当てられており、教育的ツールとしても注目
◆ 宇宙膨張の歴史を塗り替える可能性
この「高銀緯時変サーベイ」は、他の2つの中核調査(High-Latitude Wide-Area SurveyおよびGalactic Bulge Time-Domain Survey)と合わせ、宇宙の構造・進化・膨張史を、これまでにない精度と深さでマッピングしていきます。
🔭 NASAローマン望遠鏡とは?
- 管理:NASAゴダード宇宙飛行センター(メリーランド州)
- 協力:JPL(カリフォルニア)、Caltech、STScI ほか
- 産業パートナー:BAE Systems、L3Harris Technologies、Teledyne Scientific ほか
🌌 関連リンク・おすすめ読み物
本記事は、記事「NASA Roman Core Survey Will Trace Cosmic Expansion Over Time」のまとめ記事です。